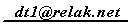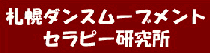精神科・心療内科領域での
ダンスムーブメント・セラピーの実践 (2009)
ダンスムーブメント・セラピー(Dance Movement
Therapy)はアメリカにおける発展の歴史を抜きにして語ることはできません。アメリカ・ダンスムーブメント・セラピー協会 (American Dance Movement
Therapy Association)は、1940年代、精神科病棟の患者さん達を対象にしてモダンダンスのレッスンを行ったマリアン・チェ
イス(Marian
Chace)らの先駆者たちによって、心理療法としての効果のあることが認められ、閉鎖病棟を含むさまざまな施設で実践される中で設立されてきたもので
す。
チェイスは、当時のアメリカの精神科医サリバン(H.S.Sullivan)による精神療法に強い影響を受け、「コミュニケーションとしてのダンス
(Dance for
Communication)」という基本を確立し、精神療法のアプローチの一つとしてダンスムーブメント・セラピーを形作っていったといえます。
-
*Sullivan, H. S.,
Interpersonal Theory of Psychiatry,
1953(中井久夫・宮崎隆吉・高木啓三・鑪幹八郎訳『精神医学は対人関係論である』1990).
ダンスムーブメント・セラピーをDance/Movement
Therapy、略してD/MTと呼ぶことに至るアメリカでの長い歴史の中で様々な観点や実践方法が育まれてきています。たとえば、現在では集団療法
(Group
Therapy)として知られているように、小集団内部での人と人とのやりとりが、ダンスを通じたグループ・ダイナミックスの力によって、豊かな体験と成
長の場となることが明らかにされたり
-
*『ダンスセラピー グループセッションのダイナミック
ス』ヘレン・ヘフコ著、平井タカネ監修、創元社1994
あるいは、個人セラピーの制約のない自由な場の中で、自らの怒りや抑鬱や喪失感をそのままに身体で表出するクライエントとのやりとりを通じて、精神分析的
な力動の観点からアプローチしたり、
-
*『ダンスセラピーノート』ジョアン・ルイン著、平井タカ
ネ監修、小学館スクウェア 2002
*『からだの声をきいてごらん』トゥルーディ・シュープ著、平井タカネ他訳、小学館スクウェア 2000
あるいは、ユング派のセラピストであるジョアン・チョドロー女史は、ユングの能動的想像法(active
imagination)を言葉やイメージの世界の中に閉じこめずに、からだがひとりでに語り出す身体的な動きや踊り(オーセンティック・ムーブメント
authentic movement)の中に展開させていきました。
-
*『ダンスセラピーと深層心理』ジョアン・チョドロー著、
平井タカネ監修、不昧堂出版 1987
このようにして成立してきたアメリカのダンスムーブメント・セラピーは、精神科を中心とした病院や医療福祉施設での実践が中心となっていたため、現在では
大学院修士レベルの専門的教育を前提にしてダンスセラピスト資格(D.T.R, Dance Therapist
Registered)が認定されるようになり、臨床心理士や看護師と同等の資格として扱われている州もあります。
さて、国内では、そうしたダンスムーブメント・セラピーに触発された活動が1960年代頃から盛んになり、1992年に「日本ダンス・セラピー協会」が設
立されるに至りました。それは、しかし、アメリカのダンスムーブメント・セラピーをそのまま輸入したのではなく、歴史・風土・文化の異なる日本独自の踊り
や身体技法なども取り込みつつ展開されることになりました。そうした経緯については協会事務局長・町田章一先生の解説にみることができます。
-
*『ダンスセラピー 芸術療法実践講座5』飯盛真喜雄・町
田章一編 岩崎学術出版社2004
そのため、日本のダンスセラピー、ダンスムーブメント・セラピーは、背景をアメリカの精神科での医療的臨床活動におきながらも、福祉・教育・地域・芸術・
身体技法といった領域での心理療法的アプローチを必ずしも排除しない、多様な内容をもつ方法として展開されてきているのです。
たとえば、日本発の前衛舞踊である「舞踏 Butoh」は、その身体的技法や精神性において創始された当時から心理療法的側面をもっており、たとえば、日本ダンス・セラピー協会副代表の岩下徹氏は国際的に有名な山海塾の舞踏手として長年活動しながら、精神科でのセラピー・プログラムを行ってきていること、精神科ディケアで「リラクセイション」「ダンスセラピー」プログラムを10年にわたって継続している葛西俊治やまた竹内実花氏も、舞踏の方法を基本にすると同時に竹内敏晴レッスンや野口体操やボディラーニングセラピーを下地にするなど、文化的歴史的影響は大きいといえます。
精神科・心療内科などの臨床場面において
身体的セッションを行っている方へ
「ダンスセラピーとは踊ることで元気になる」という一般的な見方は基本的には誤解だということを知っておいてください。特に一般の方はアメリカで始まったダンスムーブメント・セラピー(Dance Movement Therapy)の歴史と実際の内容を知る機会もなく、「ダンス」と「セラピー」という言葉を頭の中でイメージ的に結びつけて「ダンスセラピーって踊って元気になることだ」と考えてしまいがちです。
そうした当て推量による見方が世の中に流布しているためなのか、医師や看護師、臨床心理士、作業療法士、精神保健福祉士など、精神科や心療内科の現場で働く人達の中においてすら、そうした誤解が根強くあることに驚かされてきました。いわく「踊ることで精神的心理的問題が解決するならば精神科や臨床心理士はいらない」「ダンスがセラピーになるはずがない」「元気になるだけでは心理的問題は解決できない」等々…。そうした誤解の多くは通俗的な理解をそのままうけとったもので、煎じ詰めて言えばダンスムーブメント・セラピーの全体像ではなく、「運動療法としてのダンス」「運動処方としてのダンス」という側面のみを強調したために起きた誤解といえます。
そうした誤解をさける意味でも、また、アメリカでのDance Movement Therapy (D/MT)という歴史的展開を尊重する意味でも、「ダンスムーブメント・セラピー」ときちんと呼ぶことが大事だといえます。
踊るということだけではなく、身体的な動きや動作や姿勢に関わる体験の中で心理療法的な展開が行われていくこと…この点を明確に指し示すためにも「ダンスムーブメント・セラピー」という言葉を使うべきだと思います。(ただし、少し長くなるので結局は短くダンスセラピーと言ってしまいそうなのが難点です。)
身体心理療法の一つであるダンスムーブメント・セラピーについての私自身の最近の定義は次の通りです。
定義:
ダンスムーブメント・セラピーとは、「人間的で支援的な関係の場において、身体で実際に何かを行って体験していくことに備わっている身体心理的な気づきを活用して認知的および行動的変容をもたらすことに基づく心理療法」です。
また、ダンスムーブメント・セラピーの実践に際しては
- セラピーの明確な目的
- 目的を実現するための方法と方法論
- その方法を遂行するための実践的技能
以上の三点が大前提であることは言うまでもありません。
|
ダンスセラピーというアプローチには、健康体操
的であったり、運動療法的であったりする部分もあります。しかし、それだけでは、心理的な問題や悩みを適確に把握して改善に向かう心理療法としての「セラ
ピー」に至るのが困難な場合があります。特に、実践の場が精神科領域などの場合、たとえば、かなり重い鬱状態の場合は健康体操的あるいは運動療法的な活動
そのものが状況をかえって悪化させる方向
に作用する可能性も指摘されています。
そうした理解をもとにアプローチしていくダンスセラピーは、「動かないこと・動けないこと・動かないでいること」をも含み、「身体として生きて在ること
を受け入れる」という深い次元にまで至るものとなります。
精神科領域に
限らず、物事に対する考え方や行動のあり方を何らかの方法でより望ましい方向へ導くことが「セラピー」の本質を構成している以上、認知的および行動的変容
に向けた適確なアプローチについてよく理解しそれを実行するに足る技量が必要となってきます。
このように、健康体操的あるいは運動療法的なアプローチに
留まらないダンスムーブメント・セラピーに関連しては『身体心理療法の原理とボディラー
ニング・セラピーの視点』が参考になると思われますのでご一読をお
勧めいたします。
★
2007年10月、ヨーロッパの19ヶ国のダンスセラピスト達が一同に集まり、ヨーロッパ全体でダンスムーブメント・セラピーの内容・資格・教育・指導・社会的展開などについて突っ込んだ話し合いが行われ、ヨーロッパのダンスムーブメント・セラピーは新しい局面に入りました。
その後、2008年にイギリスで行われた全英心理療法評議会(UKCP)では"About a body: Working with the embodied mind in psychotherapy"、すなわち「身体について―身体化された心に働きかける心理療法」という展開をみるとともに、イギリスでは"Dance Movement Psychotherapy"を略してDMPと呼ぶことになりました。すなわち、D/MT(ダンスムーブメント・セラピー)と呼ぶアメリカとは一線を画した名称「DMP(ダンス・ムーブメント・サイコセラピー)」を採用したことになります。
なお、心理療法に身体的要素が組み込まれていくという展開にはいくつかの要因がありますが、例えば、非常に重く複合的なトラウマ体験によると考えられている「境界例人格障害 Boderline Personality Disorder」や「解離性人格障害 Dissociative Identity Disorder」といった事例の場合、そうした困難に向かっていく際には、セラピスト側もクライエント側も、身体的要素を除外するわけにはいかないという実際上の理由もあるわけです。そうした必要性も含んで、身体心理療法の一つのアプローチであるダンスムーブメント・セラピーはますますその意義と必要性を増しているといえます。
★
2009年度(2009年〜2010年3月末)まで、葛西はイギリスはロンドン近郊のハートフォード大学(University of Hertfordshire)に一年間留学し「ダンスセラピー」について研究を行いました。なぜイギリスでなぜその年度だったかというと、2010年からイギリスのNHS(National Healthe Service:日本の厚生労働省に当たる)がイギリスの「ダンスムーブメント・サイコセラピー Dance Movement Psychotherapy」を医療機関における正式の職業・職域として認定するという流れがあったためです。
そうした歴史的展開に関わった一人がダンスムーブメント・サイコセラピストであるHelen Payne教授であり、ハートフォード大学にてダンスセラピーやオーセンティック・ムーブメントについての研究、実践、指導を行い、ダンスムーブメント・サイコセラピーの有効性を立証するのに極めて大きな貢献をした方でした。(詳細はこちらをご覧下さい→ [イギリス・ダンスセラピー研究])
近年のミラー・ニューロンについての研究に基づいて、自閉症児の対人関係訓練のために小さな男の子型ロボットを用いて,関わり方を指導教育していたのは、Ben Robin教授です。この方は実はダンスセラピストで、そうした経歴と非言語的感性に基づいて、自閉症児を的確に導いていたという印象があります。(この内容はこちらをご覧下さい→[自閉症の子どもとロボットとのミラーリング])
イギリスでの資格の国家的に承認、そして、ミラー・ニューロン研究と実践の結びつき…。そうした展開の場に一年間、身を置いて感じたことは、従来の言語的カウンセリングに勝るとも劣らず、ダンスセラピーなどの非言語的アプローチの重要性と将来性でした。日本はこうした流れに乗り遅れている後進国ですが、正式な国家レベルでの資格認定の有無にかかわらず、ダンスセラピーの実践とその効果を着実に積み上げて行ければと考えています。(8/5,2011追加)
現在、札幌ダンスムーブメント・セラピー研究所に所属するスタッフは、精神科ディケアや大学の臨床心理学科での実習指導あるいはカルチャーセンターなどに
おいて、「ダンスムーブメント・セラピー(一般および認知症高齢者など)」「リラクセイション(一般および鬱病など特定の参加者向け)」「ボ
ディラーニング・セラピー」「リワーク」といったプログラム名称で指導を行っています。
そして、施設やイベントにおける集団の構成(年齢・男女・心身の状況など)によって、動いたり踊ったりすることが中心になるもの、グループのダイナミック
スやSST(社会的技能訓練)的な展開をみるもの、リラクセイションや心身の感覚覚醒をテーマとするもの等、その場で必要とされる事柄を適切に展開するた
めのノウハウ(実践的方法と理論的把握)を積み重ねてきています。
札幌ダンスムーブメント・セラピー研究所には、現在、認定ダンスセラピストである竹内実花と、同じく認定ダンスセラピスト・協会理事である葛西俊治(札幌学院大学臨床心理学科教授)が所属し、
ダンスセラピーに関連する資
格取得を希望する研究所会員へのサポートを行っています。特に研究所指導員資格の取得を目指す会員に対して、その一つ上の要件が求められる日本ダンス・セ
ラピー協会認定資格「アソシエイト・ダンスセラピスト」の取得に向けた支援および研鑽を援助する活動も行っています。
札幌ダンスムーブメント・セラピー研究所は、札幌近郊・道内を中心に、ダンスムーブメント・セラピー的な活動を行っている方、そうした活動を考えられてい
る方との連携および支援を行っていますので、具体的な内容について関心のおありの方は下記までお尋ねください。
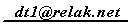
(解説 by 葛西俊治 2009)
※詳細については下記のリンクから
「札幌ダンスムーブメント・セラピー研究所」サイトをご覧下さい。
|